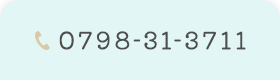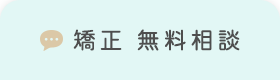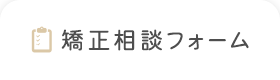口腔外科では、顎関節症の治療や親知らず抜歯、外傷に対する対処、粘膜のトラブル処置などを行います。
顎関節症

顎にはたくさんの神経が通っており、筋肉と関節が複雑に重なり合って上あごと下あごが繋がっています。物を噛むときや会話するときに、上下が連動して口が動きます。 顎の周辺に何かトラブルが生じて、口が開かなかったり、痛みが出てきたりするのが顎関節症の症状です。
顎関節症の原因
顎関節症には様々な原因が考えられます。
特に多いのが、歯の嚙み合わせが乱れている場合です。さらに、よく強い力で噛みしめていたり、あくびなどで口を大きく開けすぎたりしても顎関節症の原因になります。また、緊張したときやストレスがかかったときに、顎の周辺に力が入り筋肉がこわばってしまうことで、顎関節に炎症が出てしまう方もいらっしゃいます。
顎関節症の症状
顎関節症には、大きく分けると3つの症状があります。
顎関節雑音は顎を動かしたときガクッと音がなる、顎関節痛や咀嚼筋痛は顎が痛い、開口障害は口が大きく開かなくなる症状です。
これにより、大きい食べ物が食べられない、硬い物が噛みにくい、顎の音が気になるなど日常生活にも影響が出てきます。
顎関節症の検査
基本的に顎関節症は歯科医院で治療します。痛みの症状が顔や耳に現れる方もいらっしゃいますが、その場合も耳鼻科や内科に行くのではなく歯科医院で治療を行います。当院でも顎関節症の治療はできますので、顎関節症と疑われる方はお越しください。
1. 問診
顎関節症の治療前に、患者様の症状や健康状態などを詳しく問診いたします。
アレルギーの有無や顎関節周りの状況(口の開け閉め、顎関節の音、痛み)、どのような症状にお悩みなのかを始めに検査することが重要です。さらに、歯ぎしりや食いしばりの癖、身体の不調はあるか(肩こり、寝つき、頭痛、ストレスを感じる)などをしっかり検査します。
2. 視診
患者様を全体的に目でチェックして、トラブルがないかを診察します。
具体的には、顔の対称具合、歯の擦り減り、噛み合わせのチェック、姿勢、口腔内の粘膜に歯の痕はないかをチェックします。
3. 触診
患者様の顎や顔の筋肉に触れて、こわばりや痛い箇所(圧痛)がないかを調べます。さらに、口の開き具合、顎の動き方(前、後ろ、横)などを検査していきます。
顎関節症の治療
スプリント療法
最も良く行われている治療法は、スプリントというマウスピース状のものを使った治療法です。眠っている間に、スプリントを装着することで、歯ぎしりによる顎への負担を軽くし、症状を和らげます。
かみ合わせの調整
かみ合わせが原因と考えられる場合、かみ合わせの調整を行うこともあります。また矯正治療を視野に入れることもあります。
薬物療法
顎の痛みが強い場合、鎮痛剤や、筋肉の緊張を和らげるお薬を服用して頂だくこともあります。
日常生活上でのアドバイス
顎に負担をかけないための日常生活上での注意事項もお伝えします。例えば、「頬杖をつかない」、「歯を食いしばらない」、「あくびをする際に大きく口を開けない」といったことなどをお伝えいたします。
顎関節症でやってはいけないことは?
歯科医院で顎関節症と診断された方は、日々の暮らしで顎関節に負担がかかる行為はお控えください。また、ご自分で治療に似た行為を行うのは無駄ではありませんが、口腔内に違う異常が発生したり、症状がさらに悪くなったりする恐れがあります。当院にご来院頂き、専門知識を持つ歯科医師から適切な治療を受けましょう。
顎関節症の治療には、歯ぎしりや食いしばり、歯を嚙み合わせる癖のような自覚症状がないものの治療も含まれます。
歯・顎に関する習慣
- 歯ぎしりや食いしばり
- 物を決まった方で噛む
- 歯を無意識に嚙み合わせる(歯列接触癖)
- 顎に負担をかけた姿勢
自己判断での治療
- 薬局などに売っているマウスピース
- 誤ったほぐし方
- 整骨院や整体で治そうとする
- ガムをずっと噛む
親知らず抜歯
 親知らずというのは、思春期以降くらいから生えてくる奥歯で、2本の大臼歯のさらに奥、前から数えた場合、8番目にあたる歯です。硬いものをよく食べていた太古の昔にはそれなりの役割を果たしていたと言われていますが、現在ではあまり必要性がなくなり、もともと親知らずがない人も増えてきています。また、顎の骨のスペースが足りずに倒れて生えてくることも珍しくありません。そのため、様々なトラブルを起こすことも多く、抜歯をすすめられることの多い歯です。
親知らずというのは、思春期以降くらいから生えてくる奥歯で、2本の大臼歯のさらに奥、前から数えた場合、8番目にあたる歯です。硬いものをよく食べていた太古の昔にはそれなりの役割を果たしていたと言われていますが、現在ではあまり必要性がなくなり、もともと親知らずがない人も増えてきています。また、顎の骨のスペースが足りずに倒れて生えてくることも珍しくありません。そのため、様々なトラブルを起こすことも多く、抜歯をすすめられることの多い歯です。
当院では、親知らずの抜歯を行う際、生え方などの条件によっては保険でCT撮影を行うことが可能です。CTを撮ることで、レントゲン写真だけでは分からないような、親知らずの位置や形、埋まり方を3次元的に確認することができるので、より安全に、そして短時間で親知らず抜歯をすることができます。
外傷に対する対処
歯をぶつけてしまった、お口の中を傷つけてしまったというような場合、できるだけ時間をおかずに早めの対処が肝心です。特に歯に外傷を受けた場合、早めの対処をするかどうかで歯の寿命が変わってくることもあります。当院では外傷を受けた方はなるべく早めに対応させて頂だいておりますので、できるだけ早くご連絡ください。
歯を強くぶつけた際の注意点
- 見た目に異常が見られなくても念の為、ご連絡ください。
- 歯の破片があれば、乾燥させないようにしてお持ちください。
- ご自分で欠けた破片を接着剤でくっつけることは避けてください。
- 歯が脱臼して抜けた場合、早めの対処で戻せる可能性があります。この際、歯根部の表面にダメージを与えないよう、歯根表面には触れず、地面に落ちた場合は流水でサッと汚れを落とし、生理食塩水か牛乳に浸し、乾燥させない状態でお早めにご来院ください。
口内炎
長引く口内炎は要注意
 口内炎は、物理的な刺激やビタミン不足、ストレスなどが原因とされていますが、通常は1〜2週間くらいで自然に治ります。もし2週間以上経っても全く軽快する気配がない場合、単なる口内炎ではない可能性もありますので、念のために一度受診されてください。
口内炎は、物理的な刺激やビタミン不足、ストレスなどが原因とされていますが、通常は1〜2週間くらいで自然に治ります。もし2週間以上経っても全く軽快する気配がない場合、単なる口内炎ではない可能性もありますので、念のために一度受診されてください。
口内炎の治療
口内炎の場合、基本的には自然治癒で治るのを待ちます。ですが痛みが強い場合には、口内炎用の軟膏やレーザー照射により、痛みを和らげることができます。なお、お口の中は清潔にしておいた方が治りが良いので、お口はきれいに保つようにしましょう。
口腔乾燥症(ドライマウス)
 ドライマウス(口腔乾燥症)は口腔内が乾燥する症状を指し、病気というわけではありません。ドライマウスは様々な要因が重なることが原因で発症してしまいます。ドライマウスを発症している方は近年増加傾向にあり、その中でも発症しやすいのが女性です。また、現代人の生活習慣に関わりがあると考えられています。
ドライマウス(口腔乾燥症)は口腔内が乾燥する症状を指し、病気というわけではありません。ドライマウスは様々な要因が重なることが原因で発症してしまいます。ドライマウスを発症している方は近年増加傾向にあり、その中でも発症しやすいのが女性です。また、現代人の生活習慣に関わりがあると考えられています。
ドライマウスは口腔内が乾燥するだけなので、多くの人は病院を受診せずに放置する方が多いです。しかし、ドライマウスは私たちの健康を脅かす場合もあります。
様々なトラブルに繋がる
通常、口腔内は唾液で湿っており、この唾液は大切な役割を持っています。
例えば、口腔内を中性に維持する、口腔内のケガ予防、口腔内を抗菌して清潔に保つ、食べ物の消化を促進、初期虫歯の再石灰化を促進、感染病から守るなどの役割があります。
ドライマウスにかかり唾液の量が減少すると、様々なトラブルに繋がる恐れがあります。
さらに、ドライマウスの方がセルフケアを怠たり、甘いものばかりを食べていると、口腔内を洗浄する唾液が少ないので、汚れ(プラーク)は蓄積されて細菌が増殖してしまいます。そして口腔内にいる細菌は、歯や歯茎を支える骨を少しずつ破壊していきます。
日常生活の中で可能なドライマウス予防
日常生活でちょっとだけ意識することで、ドライマウスの改善が期待できます。
- お酒、タバコ、カフェインの摂取をなるべく控える
- よく噛む物を食べる(硬い物)
- 顔の筋肉を刺激するため歌う
- 鼻呼吸を意識する
- ストレス発散する
- 部屋の中を加湿器で乾燥対策する
- 早寝早起きを身につける
- 健康を心がける
- 休息の時間を設ける
- 会話をする